法律面で見る勤務医の退職トラブル【荒木弁護士解説】
~退職に関する法律とよくあるトラブルの対処法~
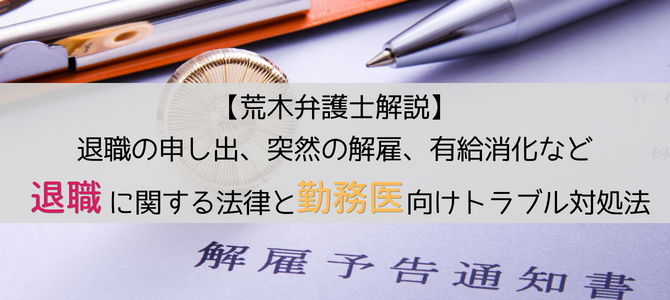
~退職に関する法律とよくあるトラブルの対処法~
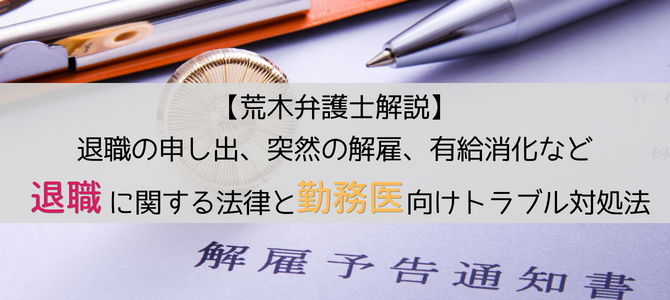
勤務医の転職時期は、3月末退職4月入職に集中するのが特徴だと思います。医師の皆様の中には、程度の差はあれど退職時に医療機関と揉めたり不本意な思いをしたりした経験がある方も少なくないのではないでしょうか。また、医局を退局するのに大変な思いをしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、知っておくといざというときに役立つ退職に関する法律上のルール、退職時によく起きるトラブル、そして、アンケートで寄せられた実際のトラブルをご紹介したいと思います。

他の記事を読む